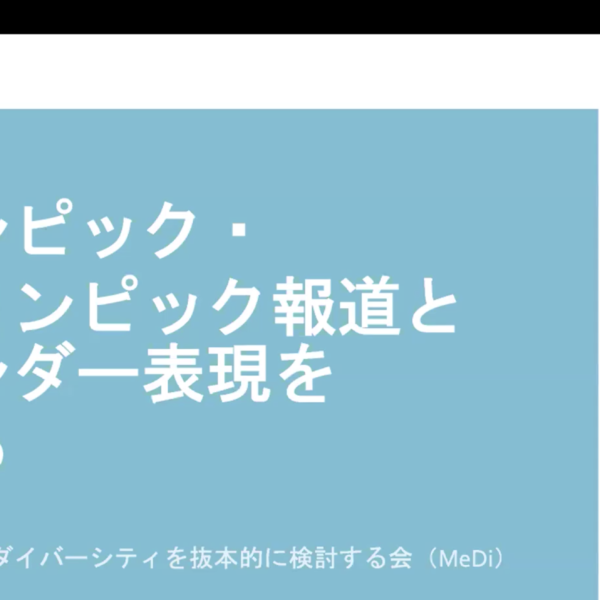B’AI グローバル・フォーラムを拠点として活動する産学共同研究グループ「メディア表現とダイバーシティを抜本的に検討する会(MeDi)」は2021年8月28日(土)、「オリンピック・パラリンピック報道とジェンダー表現を考える」というテーマで非公開のオンラインワークショップを開催した。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は、大会のビジョンの一つに「多様性と調和」を掲げ、それを実現するためにジェンダー平等の推進を重要な課題として設定していた。実際、オリンピック出場選手の約49%を女性が占めるようになり(パラリンピックでは40.5%)、男女混合種目も前回リオ大会から倍増して計18種目となったことやトランスジェンダー選手が出場する史上初の大会となったことなど、形式的な面ではジェンダー平等に一歩近づいたと評価される。一方で、大会を人々に伝える「報道」の面ではどうだったか。大会期間中に開かれた本ワークショップでは、メディアの現場でジェンダー課題に取り組む実務者と研究者が集まり、今回のオリンピックにおける報道の具体例を挙げながらジェンダー表現の実状を検証し、より良い報道の実現に向けて意見交換を行った。
- 日時:2021年8月28日(土)10:00~12:00
- 形式:オンライン
- 参加者:32人(MeDiメンバー、B’AIメンバー、メディア関係者)
オリンピックに関する様々な論点
ワークショップは、ファシリテーターを務めたMeDiメンバーの治部れんげ氏(ジャーナリスト、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授)のガイドに沿って「①全体で問題意識を共有 ②グループワーク ③各グループで話し合った内容を発表」という3部構成で行われた。
冒頭の開会挨拶で、MeDi座長の林香里教授(東京大学大学院情報学環、東京大学副学長、B’AIグローバル・フォーラムディレクター)は、オリンピックとは近代という時代のあらゆる負の側面、すなわち帝国主義、レイシズム、ナショナリズム、セクシズム、進歩主義、商業主義などを足掛かりにして成長してきたという面で暗いテーマでもあると指摘した上、それはもう一つの近代の所産であるジャーナリズムと重なる部分も多く、ジャーナリズムのあり方をオリンピックという写し鏡を通じて考えるということは近代を見直す作業でもあると、本ワークショプの意義を語った。
続いて、オリンピックにまつわる様々な論点を参加者全体で共有するために、研究者側と実務者側がそれぞれの視点から発表を行った。まず研究者側からはMeDiメンバーの田中東子教授(大妻女子大学文学部)が、そもそもオリンピックとは何かを近代オリンピックの出発点に遡って歴史的に解説し、その発展過程における諸問題をセクシズム、レイシズム、ナショナリズム、コマーシャリズムという4つのテーマに分けて整理した。
19世紀終わりに始まった近代オリンピックは、「スポーツを通じて人間としての優れた精神性を獲得する」という理念を持っていたフランス人のピエール・ド・クーベルタン男爵が主軸となり古代ギリシャで行われていた宗教的イベントを復活させたものである。しかし、田中教授によると、その理念にある「人間」とはあくまでも⻄洋中心の白人男性だけを示しており、クーベルタンはそもそも女性がスポーツに参加する意義を認めていなかったという。また、IOCは最初の約30年間オリンピックへの女性の参加を巧妙な画策で阻んでおり、1960年代には黒人公⺠権運動への賛意を示した選手たちをオリンピックから追放するなど、性的・人種的マイノリティの排除は組織的なレベルで行われていたということである。一方、ナショナリズムという面では、そもそも聖火リレーやオリンピック旗の入場など今人々が喜んで見ているセレモニーが実はナチス・ドイツが自国の力を誇示し宣伝する手段として創造したものであり、林教授らの共同研究でも指摘されているように「オリンピックは単なるスポーツイベントではなく国家の重要な課題としてメディアで取り扱われている」こと、また自国選手の活躍という視点でしか報道されないという点からも、オリンピックというものがいかにナショナリズムと強く結びついているかがよく分かると説明した。そして最後に、ジュールズ・ボイコフ教授の「祝賀資本主義(Celebration Capitalism)」という概念を紹介し、喜びや楽しさという名目で莫大な税金を投入しながらも開催にあたってその税金を払っている市民の声はほとんど反映されず、民間企業の利益だけに貢献する形でますます巨大化してきているとして、オリンピックが持つコマーシャリズムの側面を批判した。
次に報道実務者の観点からは、MeDiメンバーでNHK名古屋拠点放送局報道部副部長の山本恵子氏から発表があった。山本氏は、まず2月にあった森喜朗氏(当時の東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会会長)の女性蔑視発言に言及し、そのこと自体は日本のジェンダー意識とグローバル・スタンダードとの隔たりを露呈する出来事であったがメディアにとっては報道にあたっての課題を改め自覚する契機ともなったと述べた。しかし、実際の報道現場では依然として構造的な問題が多く、例えば報道体制の意思決定層や実況の現場などにおけるジェンダーのアンバランスは未だに全く改善されていないと指摘した。また、表現上でも、アスリートの性別によって使われる単語に違いがあるかを分析した朝日新聞の調査結果(ヤフーニュースで配信された約1万7千件の東京五輪関連記事を分析。「豪快」「強烈」「完璧」などの単語は女性選手の記事より男性選手の記事にそれぞれ約3.5倍、2.1倍、1.9倍多く使われたことに対し、「可愛い/かわいい」は女性記事で使われた回数が男性記事の2倍だった。https://www.asahi.com/articles/ASP856K8DP83ULEI006.html )などが示すように、メディアに根ざしている無意識のバイアスはとても深刻であると批判した。
このような問題提起はMeDiのメンバーだけでなく、参加者の方からもなされた。主催者側からの事前のお願いにより、それぞれ異なった媒体(テレビ、新聞、フリージャーナリスト)に従事している3人の参加者から話を聞かせていただいたところ、森元会長の発言で断的に見られたように組織委員会の中でジェンダー意識が非常に不足していることや、男子競技と女子競技に対する注目度や報道量に格差が見えてきた場面もあったことなどが指摘された。また、取材する立場で特に難しく感じたこととして、若い女性選手について報じる際にどうしてもサイドストーリーに話題が傾く傾向があり時間の圧迫の中ではその傾向がさらに強まることや、同じ社内でも例えば社会部と運動部では意識に格差がありそこから生じる困難もあること、一方でジェンダー平等の側面で問題点の多いオリンピックだが取材をしていると女性をエンパワーする面もまた非常に感じられ、だからこそスポーツの表現に関わる者として考えなければならないことが多いということなど、報道の担い手ならではの悩みや懸念を共有していただくことができた。
グループワーク
全体セッションの後は、7つのグループに分かれてさらに踏み込んだ議論に入った。1つのグループの人数は4~5人で、MeDiのメンバー、研究者であるB’AIメンバー、そしてメディア関係者である一般参加者がそれぞれ少なくとも1人以上入るように分けられた。
参加者はそれぞれ今回のオリンピック報道の中で特に気になった記事や番組の事例を持ち寄り、その表現の何が問題で、そのような表現を生み出したニュースルームの構造的な問題は何かを、事前に配布されたIOCの「表象ガイドライン」と「LGBTQ+アスリートのメディアガイドライン」、そして冒頭で発表された論点に照らし合わせながら話し合うという内容で進められた。
議論した内容の発表
35分間のグループワークの後は、各グループで話し合った内容を参加者全体で共有する時間が設けられた。個別発表に入る前に、全グループを見回ったファシリテーターの治部氏から、議論がとても多岐に渡っており、クローズドな会だからこそ率直な話ができていて良かったとの感想が述べられた。
7つのグループから発表された内容を簡単にまとめると次のようである。
まず、ジェンダーにまつわる表現の問題として最も多く指摘されたのは、女性選手の描き方においてアスリートとしての能力よりも容姿、結婚、育児などのサイドストーリーに注目する傾向が未だに存在するという点であった。そのような問題の端的な例としてしばしば話題となるのが子どもを持つ女性選手を「ママアスリート」と称し、その選手の母親という属性だけを強調するような報じ方をすることである。今回の大会では過去と比べて「ママアスリート」という表現自体は減ったものの、言葉こそ使っていないだけで内容は依然として家事や育児を女性の仕事として捉えて夫はあくまでもサポート役であるという認識から書かれた記事も多く、根本的な改善にまでは至っていないと指摘された。またこれは、女性選手の容姿を描写する際も同じで、「美しすぎる」などあからさまにバイアスがかかった表現は減っても、それは単に「可愛い」や「妖精」などに置き換えられたにすぎず、一方で新体操のような妖艶さなどが芸術性の評価基準になっている採点競技のような場合の表現の難しさにどう対応すべきかという現場での悩みも共有された。
印象的だったのは、「ママアスリート」という表現に関する話の時に、単純に母親としての表象は駄目だということで議論が終わったのではなく、出産した選手がどのように努力して復帰したかということは女性のエンパワーメントにもつながり、その選手のアスリートとしての凄さを伝えるためにもその努力にはきちんとフォーカスすべきとの意見が複数のグループから出たことである。そこで、ジェンダーバイアスを助長せずに報じる方法として、例えば、「ママアスリート」と呼ばれる時の選手本人の葛藤を取り上げたり、父親である男性選手の育児との両立を取り上げる記事を増やすことでバランスを取ることもあり得るなどの提案がなされた。
この女性選手に限定されるサイドストーリーやそこに使われる言葉の話は自然にネットメディアとSNSという話題につながった。ジェンダーバイアスがかかっている典型的な表現としての「ママアスリート」や「美しすぎる」などの言葉は、新聞や地上波テレビでは減ってもネットメディアでは相変わらず多く使われているのが現状だからである。ネットメディアは、大量の他の記事との競争の中、短時間でオーディエンスの目を引くためにあえて見出しにステレオタイプ的な表現を使う傾向があり、今回は特にLGBTQ+選手の記事で多くの例が見られたという。近年ニュースメディアとしてより利用されているのがネットメディアであり、またアクセスのしやすさから子どもへの影響が大きいことを考えると、ネットメディアの表現ルールについても見直しが必要なのではとの意見が出た。
一方、テレビについても、事前に用意される原稿の中では概ねジェンダーバランスが取れるようになっても、キャスターやコメンテーター、インタビュイーなどがその場で発する言葉の中から無意識のバイアスが非常に出てきやすいことが話題になった。その例として、野球評論家の張本勲氏が朝の報道番組に生出演し、ボクシング女子フェザー級で金メダルを獲得した入江聖奈選手に対し「女性でも殴り合いが好きな人がいるんだね、見ててどうするのかな?嫁入り前のお嬢ちゃんが顔を殴り合ってね。」などと発言したことや、名古屋市の河村たかし市長がソフトボール日本代表後藤希友選手の金メダルをかじったことなどが挙げられた。河村市長のメダルかじりは、そのことだけでなくその前後にセクハラ発言があったことが後から明らかになってさらに波紋を呼んだ。そしてワークショップ参加者から、そのような前後の発言について最初は報道がなかったこと、そして現場にいた記者からその場で問題提起されなかったことについて自己反省の声も出た。
これら不適切な発言の例においても、また女性選手に対するバイアスがかかった表象についても、その根底に共通する問題は、そもそも女性選手に対する敬意が欠如していることである。そのような敬意の欠如は舞台の裏側でも見られ、例えば40-50代の女性選手やコーチに対する同じ年齢台の男性ディレクターの態度が厳しかったり、扱いが小さかったりなどの差を感じるという参加者もいた。また、同じ社内でも社会部と運動部ではジェンダー意識に差があり、両者が出す記事を比較するとその差が反映されているのが分かるとの指摘もあった。ただこれは、報道とはやはり関わる人の構成によって内容が変わるものであって、一人ひとりの意識をあげていくことで改善できる話でもある。だからこそ今、各社がしっかりジェンダー研修を行う必要があり、その実現のためにも、ジェンダー意識の大事さを訴える人を社内で正当に評価することが先行されなければならないと強調された。
今回のワークショップは、オリンピック・パラリンピック大会の最中で、報道の担い手たちが現場で感じる問題点や悩み、モヤモヤした気持ちを、同じ立場にいる仲間たちと率直に話し合うことで横の繋がりができたという点でとても意義があったと思う。特に、普段は意見交換する機会が少ない実務者と研究者が論点を出し合い、オリンピックとその報道に関するお互いの問題意識がさらに深まったということで、B’AIとMeDiの目標であるフォーラム形成という意味でもとても有益な場であったと言える。