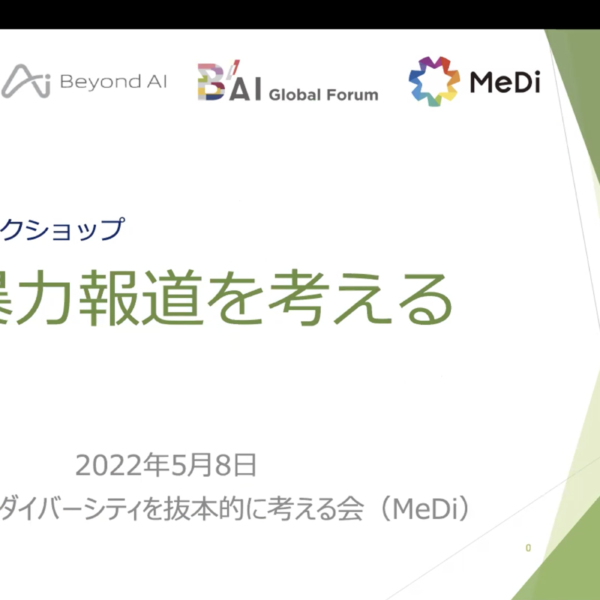東京大学B’AIグローバル・フォーラムを拠点として活動する産学共同研究グループ「メディア表現とダイバーシティを抜本的に検討する会(MeDi)」は2022年5月8日(日)、「性暴力報道を考える」というテーマで非公開のオンラインワークショップを開催した。政治、社会、教育、家庭など、様々な場で起こっている性暴力に対し、ジャーナリズムがどのように対応してきたのか、どのような課題があるのかを、報道現場の実務者らとともに検証し、より良い報道に向けて意見交換するための企画である。当日は、MeDiメンバーの山本恵子氏(NHK解説委員 名古屋放送局コンテンツセンター副部長)が進行役を務め、同じくMeDiメンバーで東京大学大学院情報学環准教授の李美淑氏、性暴力被害当事者ら団体Springの代表を務める佐藤由紀子氏、元朝日新聞記者で東京大学大学院情報学環特任教授の河原理子氏が登壇し、それぞれ、研究者、当事者、ジャーナリストの立場から性暴力報道をめぐる論点の整理と問題提起を行った。その後、グループに分かれて参加者それぞれの経験を交えながらディスカッションし、最後にその内容を全体で共有した。
- 日時:2022年度5月8日(日)13:00-15:00
- 形式:オンライン(Zoom Meeting)
- 言語:日本語
- 参加者:32名(MeDiメンバー、B’AIメンバー、メディア関係者)
性暴力報道とジャーナリズム ― 権力監視、公共性、メディアへの信頼
冒頭の挨拶でMeDi座長の林香里教授(東京大学大学院情報学環)は、性暴力・性犯罪報道をジャーナリズムという大きなコンテクストの中に位置付けた時に考えるべきこととして、権力の監視、公共性の問題、メディアへの信頼という3つを取り上げた。林教授によると、ジャーナリズムの最も重要な機能は権力監視であり、性暴力というのは強制、権威、操縦などのストラテジーを使った究極な形の権力濫用であることから、この性暴力についてしっかり報道するのはジャーナリズムの果たすべき責任であると言える。しかし、圧倒的に男性によって振るわれてきたこの種の性暴力・性犯罪をジャーナリズムは監視しきれてこなかったのでその点を反省する必要がある。そして、2点目の公共性の問題について林教授は、公共性という概念に男性中心の考え方が横たわっている側面があるにもかかわらずこれまで非常にポジティブに捉えられてきたことを批判し、性暴力報道にあたっては公共性や公共圏などの論理を安易に当てはめるのではなく、女性やマイノリティ、被害者の視点から取材や情報公開のあり方について考える必要があると指摘した。最後にメディアへの信頼については、アメリカの映画プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインによるセクシュアルハラスメントを暴いたニューヨークタイムズの報道を話題に挙げ、ジャーナリズムの大原則ともされてきた十分な裏とりや実名証言が特に重視されるという面で、性暴力報道とはまさにその社会におけるメディアへの信頼度が問われるバロメーターのようなものであるとの考えを示した。
林教授は、上記3点が日本の性暴力報道を考える際に非常に大きな挑戦として浮かび上がってくると述べ、歴史的、制度的な社会構造とも関わるこの根深い課題についてメディア研究者と実務者が一緒に考える機会になればと、本ワークショップに込めた願いを語った。
研究者・当事者・ジャーナリストによる論点整理
開会挨拶に続く発表のセッションでは、まずMeDiメンバーで東京大学大学院情報学環准教授の李美淑氏が登壇し、研究者の視点から性暴力報道における問題点を整理した。最初に提示された内閣府男女共同参画局の「男女間における暴力に関する調査」(2021年発表、N=5000)によると、日本の女性の約14人に1人が無理やりに性交等をされた被害経験があり、被害を受けた女性の約6割はどこにも相談しておらず、その半数は相談しなかった理由として「恥ずかしくてだれにも言えなかったから」と答えたという。なぜ被害者が恥ずかしさを背負わされるようになったかについて李准教授は、「性暴力とは『まったく知らない人』による『暴行脅迫』を伴った行為」という神話が背景にあると指摘する。ここで改めて性暴力の定義を確認すると、この言葉には、性的暴行/強姦、セクハラ、性的嫌がらせ、性虐待、性搾取、痴漢、ストーキング、画像や動画を許可なく取るまたは流布させるなど、「望まない・同意のない性的な行為や発言」全てが含まれる。そして、前掲の調査によると、性暴力行為の9割近くは、交際相手や親族、学校や職場の関係者など知り合いによって振るわれている。にもかかわらず、知り合いによる行為や暴行脅迫を伴わない行為は、そもそも性暴力として認められなかったり被害者側に疑いの目が向けられる傾向があり、恥ずかしさを押し付けられた被害者が沈黙する中、性暴力がますます許容、助長されていくということである。
李准教授は、このような現状には報道のあり方も深く関わっているとし、性暴力報道に関する論点として、無報道という問題、報道内容の問題、報道における表現の問題を取り上げた。准教授によると、性暴力は長らく人々が知るべき価値のある情報と見なされず、マスメディアに取り上げられないことによって問題自体がなかったことにされてきた。特に日本では、政治家や著名人など社会的地位のある人から受けた性暴力の告発がメディアの無関心の中で揉み消されたりエンタメのネタとして消費される事例も多く、これらが沈黙を強いる社会的メッセージとなり被害者をますます萎縮させてきたという。一方、報道の内容については、性暴力を生み出す社会文化や男女の権力不均衡といった構造的背景には目を向けず、あくまでも「加害者個人の逸脱」や「事実関係を争う個人間の私的な問題」として扱う傾向が強く、その中の表現を見ると、被害者の「落ち度」に注目する表現、加害者とされる人の供述をそのまま伝える表現、「乱暴」、「わいせつ」、「みだらな行為」など性暴力を矮小化するような表現、「援助交際」や「枕営業」など性搾取をごまかすような表現が多く使われていると指摘した。李准教授は、これらがもたらす結果として、被害者側に責任があるかのような印象が作りあげられる、性暴力の深刻さが軽々しく伝えられる、レイプ神話が再生産されるなどの問題点を挙げた上、性暴力根絶のためにはよりサバイバーの視点に寄り添った報道が必要であると訴えた。
続いて、性暴力被害当事者ら団体である一般社団法人Spring代表理事の佐藤由紀子氏が登壇した。ご自身が被害当事者であり、性暴力対策アドバイザーとして被害者や若年女性の支援に関わっている佐藤氏からは、これまで100件近くの取材を受けてきた経験に基づき、性暴力被害者にとって安心して受けられる/受けられない取材とはどういうものなのかについて知見を共有していただいた。
佐藤氏はまず、被害者に安心して取材を受けてもらうために記者にできる工夫としていくつかの事前準備を提言した。例えば、インタビューで何を聞きたいかを事前にメールで知らせること、取材自体や質問内容について断っても良いという選択肢を与えること、インタビュー中にしんどくなったら休憩を入れても良いと事前に伝えること、記事を公開する前に本人に確認してもらい必要な場合は修正希望を伝えられるようにすることなどが提言された。そうすることで、取材を受ける側は「自己決定権」や「安全感」、「有力感」を確保できるという。ここで佐藤氏が強調したのは、これらは全て性暴力で奪われた感覚であるということだった。被害者が性暴力で体験した「不意打ち」、「驚愕」、「困惑」などの感覚を蘇らせないためにも、次にどんなことが起こるかを予想できる取材の場を作ることが大事だということである。
それでは、逆に安心して受けられない取材とはどういうものかというと、佐藤氏は、質問の内容が漠然としている取材と自分の被害をジャッジされる取材を例として挙げた。前者は、どこからどこまで話せばいいか分からず、不意に聞かれた質問でトラウマ反応が強く出るかもしれないので不安になり、後者は、被害体験そのものを否定される可能性を孕んでおり、それがさらにWEB上でのセカンドレイプにつながる恐れがあるので不安になるという。また、被害の詳細を尋ねる質問として、「どうして」や「なぜ」と聞かれると強い自責感に駆られるようになるので、代わりに時系列を聞くような表現である「どういう経緯で」の方が良いとのアドバイスもなされた。
最後に、これまで取材を受けてきて感じたこととして、女性の取材者だからといって必ずしも正しい理解があるわけではないことや、「被害にあった人は笑わないはず」とか「普通の日常を楽しむことができない」といったステレオタイプな被害者像を押し付けられるのはナンセンスであることなどが挙げられた。佐藤氏は、トラウマ回復のために必要なのはやはり「人とのつながり」や「社会での居場所」を感じられることであり、どちらも取材者とのやり取りでできていくものなので、それを大事にしていただければとの願いを付け加えた。
続いては、元朝日新聞記者で30年近く性暴力取材に携わってきた河原理子氏より、取材する側として感じる課題や取材にあたって最低限知っておくべきことについて話していただいた。河原氏はまず、朝日新聞の過去記事で「性暴力/性的暴力」というキーワードが出現する記事件数の推移データ(1985年~2021年)を提示し、マスメディアによる性暴力報道の量的変化に言及した。データによると、1980年代には皆無に等しかった記事数が90年以降右肩上がりで増加し、ピークに達した2020年には300件を上回っている。河原氏は、この一つの要因として性暴力問題に関心を持つ女性記者の増加を挙げ、女性と男性の違いは被害経験が身近であるかどうかという経験値の圧倒的な差であると述べた。ただ、佐藤氏の話にもあったように、女性だからといって必ずしも正しい理解があるとは言えず、性別にかかわらず取材に関わる全ての記者は性暴力報道特有のスキルと知識を身につけなければならないと指摘した。また、性暴力報道には、取材そのものの難しさや事実確認の難しさがつきまとうだけでなく、社会や報道機関内部にも根強く存在する無理解や偏見に働きかけながら、「日常化された異常性」を明らかにして意識を変えていく姿勢が求められることも指摘した。
それでは、性暴力取材にあたって必要な知識にはどういうものがあるのか。河原氏は、事前に配布していた2つの資料、「性暴力被害取材のためのガイドブック」(性暴力と報道対話の会、2016)と「Reporting on Sexual Violence」(Dart Center Europe、2011)を参照しながら、性暴力取材で最低限知っておくべきこととして4点を挙げた。①基本ルールが異なる(企業や役所、有名人などを相手とする通常の取材とは違う態度が必要)、②トラウマ反応について知る(特に、被害者の自責感など)、③経験者の思いや反応は一人ひとり違うことを理解する(ステレオタイプな「被害者らしさ」を当てはめない)、④取材する人自身もダメージを受けることがあるので、セルフケアの必要性を知り予め備える。
質疑応答
登壇者の発表の後は、参加者から事前に受け付けていた性暴力取材にあたっての悩みや質問に答える時間が設けられた。被害者のトラウマや二次被害の恐れなどを念頭において常に悩みながら奮闘している記者らが集まっただけに、「被害状況をどこまで詳細に聞けば良いか」「どこまで詳細に記事を書くべきか」「加害者の言い分をそのまま伝えても良いだろうか」など、取材過程や記事の執筆における具体的な質問が寄せられた。
まず、「記事でどこまで表現するか」の問題について河原氏は、正解はないので毎回悩みながら書くしかないとした上で、被害状況の深刻さを伝えることを目的として詳細に書いたとしても別の興味で読まれてしまい二次被害につながる可能性もあることを念頭におく必要があると指摘した。また、インタビューの時に「どこまで聞くか」ということについては、これも唯一絶対の答えはないので相手をよく見て相談しながら進めるしかなく、自分の場合は、質問したい内容とその趣旨を伝えた上で、辛かったら答えなくても良いという選択肢を最初に明確に示して、不安なことがあれば遠慮なく言ってほしいと伝えるように努めていると述べた。このような進め方について、取材を受ける側である佐藤氏も賛同し、例えば、聞きたいことを箇条書きにして話せるところを被害者に選んでもらい、もし全部答えたくなければそれでも大丈夫だと伝える、といったようなやり取りをしていただければと補足した。
一方、複数の参加者から寄せられたのが「加害者の言い分をどのように伝えれば良いか」という質問だった。報道倫理規定などにもあるように加害者側(被疑者、被告人など)からのコメントも伝えなければならないのは確かそのとおりであるが、どんな理不尽な言い分でも伝えなければならないのか、それが被害者をさらに傷つけてしまうのではないかと躊躇うこともあるという悩みの声であった。これに対して、河原氏は、自らの反省も込めて、原則として、どんな人であってもどんな内容でも言い分を聞くことは必要だと指摘。ただ、それで終わるのではなく、継続的に取材報道するなかで、主張の正当性やなぜそのように思ったのかを明らかにしていくことができるのではないかと答えた。一方、佐藤氏は、加害者の言い分が自分のインタビューと同じところにあるとやはり抵抗感はあるが、反証の機会を与える必要があることは理解しているので、一緒に掲載される予定であることを事前に知らせてもらえれば良いとの見解を示した。
グループディスカッション
ここまでで全体会が終わり、ワークショップはグループワークのセッションに移った。参加者は6つのグループに分かれ、各自持ち寄った記事の事例などを材料として踏み込んだ議論を交わした。各グループで話し合われた内容をまとめると以下の通りである。
まず、取材現場でぶつかる様々な壁について実務者の経験が共有された。李准教授が指摘した「無報道」の背景とも取れる話として、裁判で判決が確定していない現在進行形の事件は取り上げにくいことや、訴訟のリスクという現実的な問題があるという話が出た一方で、記者を萎縮させる要因の一つとして上がったのがセカンドレイプの問題だった。性暴力事件の実態として多いのは知人によるものやお酒が絡んでいるものだが、そのような事件ほど二次被害が起きやすいので、それについて報じることで被害者がネット上でのセカンドレイプに晒されてしまうのではないかというジレンマがあるということだった。この問題は、「被害者『らしさ』の再生産」との関連でさらに難しくなる側面もある。テレビのニュースで被害者の映像を編集する際に、ネット上で起こり得るバッシングを意識し派手な服装の場面を避けるなどといった自己規制が働くことがあるが、被害者を守るつもりでなされたメディア側のこのような選択がむしろ被害者ステレオタイプの再生産につながるのではないかという問題提起があった。
一方で、加害者についてはどうかというと、李准教授の発表や事前の質問でも話題に上がったように、加害者とされる人のコメントをそのまま伝えることに問題を感じるとの声が複数の参加者から上がった。ここで言及されたのは、犯行動機として出てくる「むらむらしてやった」という表現だった。本当に加害者の言い分なのか警察の定型文なのかも不明なこの表現については、それが繰り返しニュースに登場することで性暴力・性犯罪を過小評価してある種の神話が強化されかねないという問題や、それを女性のアナウンサーに読ませることでそのニュースが不適切な形で消費される恐れがあるといった問題が提起された。
また、さらに大きな文脈の話として、個々のケースの報道だけではなかなかその背景にある抑圧の構造までは描けないという指摘もあった。性暴力はどうしても個人間の問題に矮小化されやすく、背後にある性差別や権力関係までは議論されないまま話が終わってしまうということだった。
このような様々な課題に対して、その背景にメディア産業そのもののセクハラ体質やダイバーシティの不足といった構造的な問題があるのではないかとの意見も出た。最近、映画界では性暴力を告発する被害者の声が相次ぎ、メディア産業に根強い性搾取とセクハラの深刻さが露わになっている。ある参加者は、やはり管理職の中で性暴力がメインストリームの事案として認識されておらず、報道の優先順位でも低く評価されてしまう問題は確かにあると語った。
それでは、性暴力根絶につながるより良い報道のためにはどのような取り組みが可能だろか。グループセッションでは、問題の指摘だけでなく解決に向けた前向きな議論も交わされた。まず、セカンドレイプの防止策として、自殺に関する記事の最後にホットラインが載るのと同じように、性暴力報道でも記事の最後に二次被害についての説明を付けるようにすると、注意喚起できるとともにオーディエンスの中でも「それはセカンドレイプですよ」と指摘する雰囲気を広められるのではないかという意見が出た。一方、TikTokの場合はセカンドレイプになるような投稿をAIで感知しアラートを出したら実際に不適切な投稿が減少したということで、Twitterなどにもそのようなテクノロジーを導入したらどうかという技術的な対応策も提案された。また、そもそも記事の書き方を社会的な不公平を指摘し公正さを追求していくような書き方にすれば二次被害をある程度抑えられるのではないかという意見もあった。
一方、個々の事件の構造的背景が見えてこないという問題については、ある事件について報道する際に、類似した環境で起きた他のケースを集めグルーピングして報じるという案が示された。例えば、学校の中で起きたことなら、似たような被害の声を集めて「学校の中の性暴力」という形でグルーピングして伝えると、全て同じ権力構造の中で起きているということが見えやすく、もっと社会に訴えられる形にできるのではないかという意見だった。
そして、社内の研修や勉強会の重要性も改めて強調された。研修や勉強会はもちろん社員教育という面で第一の効果があるが、それだけでなく、社内に同じような問題意識を持っている人たちがいることを可視化できるという面でも重要であるということだった。さらに、報道全体の構造に関わるプロセスや認識を変えていくためには個別機関の努力だけでは難しいので組織を超えて横の連携を強化していかなければならず、本日のワークショップのような機会をもっと増やす必要があるとの意見もあった。
全体の内容が終わった後、登壇者の佐藤氏と河原氏に本日の感想を述べていただいた。佐藤氏は、多岐にわたる話を伺えてよかったという感想とともに、#Metoo運動が盛んに行われている中で声を上げられない被害者たちのモヤモヤを耳にすることも多いとして、声を上げる/上げないは自分の選択であって他人に強いられるものではないことから被害者がそのようなプレッシャーを感じる必要は全くなく、ただ大事なのは声を上げたいと思った時にそれができる土壌があるかどうかということなので、そのためにご自身も尽力していきたいと語った。河原氏は、一人では解決できないことがたくさんあるということがこの場で共有できたと述べ、とにかく取材を続けていって論評や企画など様々な形で発信していくこと、このように組織の枠を超えてつながり、諦めずに、問題意識を共有する仲間を増やしていくことが大事だと強調した。
性暴力報道に関してはこの場で議論できていない課題がまだまだ山積みである。ただ、同じ問題意識を持つ人々が集まりアイディアを出し合うことで少し希望が見えてきたのも確かである。このような横のつながりを強固にするためにも、MeDiとして引き続きこのテーマに注目し、より良い報道に向けた場づくりに取り組んでいかねばと考える重要な機会となった。
報告者:金 佳榮(東京大学大学院情報学環 特任研究員)